本展では新鮮な感覚を煌かせ現在活躍中の美術家たち、吉川陽一郎、多和圭三、大森博之、石川順惠、青木野枝、坂口寛敏、さかぎしよしおう による平面・立体作品を展示します。
現代の美術が、21世紀に入り、新たな指標を模索しつつ、ひとつの転換期を迎えているかに思える今日、わたしたちにとって最も身近なところで生起している日本の現代美術を、改めてじっくりと見つめなおしてみたい……「プライマリー・フィールド」展は、そんな想いを端緒に組み立てられた展覧会です。1990年頃から制作された作品に新作を交えて展覧いたします。
展覧会タイトルの「プライマリー・フィールド」とは、「原初的な場」あるいは「基本的な場所」といった意味です。本展の出品作品や作家の特徴には、「シンプルな作品の構造」、「素材の特性を生かす」、「光や空気といった場の要素を生かす」、「身体や行為と空間の関わりの重視」、あるいは「恬淡とした制作態度」といったことなどが挙げられるでしょう。それらはすべてわたしたちが「生きる」ということに関わる基本的なことであり、それらが交差し合い、静謐でありながらも根源的な力強さを語りかけてくる場となることを企図して展覧会は企画されました。
7名の現代美術家による本展は、言うなれば連続した7つの個展を訪れて、それぞれの来館者の方が、自らの目で作品や空間から、立ち上り、響き合う何かを発見し、新たな課題の所在を感じとってくださる場であればと心から願っております。
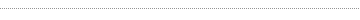
吉川陽一郎[1955-]は、薄い鉄板をハサミで紙を切るように切断し、立ち上げ、他のさまざまな素材とも接合した立体作品を制作しています。ハサミの握り手の部分やワラ積み用のフォークの先端部分、あるいは動物の骨の部分などを想わせる形体が組み合わされた、斬新で軽やかな彫刻の制作を実践し続けています。
多和圭三[1952-]は、中に隙間のない無垢の鉄の塊を、鏨のハンマーで気が遠くなるほど幾度も打ち込むという行為により、頑強でありながら不思議な艶かしさをもつ彫刻をつくり出してきました。そのたたかれた鉄の表面は波だち、光を乱反射して微妙な輝きを発して、見るものを豊穣なる沈黙の世界へと誘います。
大森博之[1954-]の作品は、やわらかな粘土の一塊から量塊を立ち上げていくモデリングによって形づくられています。やわらかな佇まいでありながら、見飽きることのない強度をもった彫刻です。何かの具体的な形象のようにも見えるその抽象彫刻は、多様な記憶や時間のかさなりといったものを感じさせるものです。
石川順惠[1961-]は、抽象表現主義やカラー・フィールド・ペインティングなど、さまざまな要素を批判的に咀嚼しつつ、独自の世界を築きあげてきた画家です。日常の生活の中で発見した形態の断片と、透明感あふれる色彩による複合的な奥行きのある絵画空間は、描くことの原初的息吹を伝えてくるかのようです。
青木野枝[1958-]は、一貫して鉄という素材を用いて、スケール感のある彫刻を制作してきた作家です。しかし伝統彫刻のもつマッス(量塊性)はなく、線や面という基本的な造形要素により空間が構成されます。光や空気を包み込んだような、浮遊感のある構築的な彫刻をつくり続けています。
坂口寛敏[1949-]は、絵画作品と立体のインスタレーションを同時に展示し、空間を構成します。坂口は作品制作について「何もないと思われるところに原初的な発生がはじまり、無から有そして再び無へと循環する世界のプロセスに自分を繋げていく。渦巻きや螺旋、円錐形といった生成と循環のエネルギーの流れに沿った形が、空間を生み、固有の場を創造する」と語っています。
さかぎしよしおう[1961-]は、近年、スポイトから磁土を一粒ずつ垂らして、上に積み上げて形態を作り、電気釜で焼く「焼き物」の技法を用いた小さな立体作品を制作しています。淡々とした原初的な作業から、まるで光の粒子が層状に重なり合い、凝縮されたような、作品という物質が発生する場へと見る者を誘います。
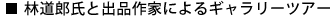 |
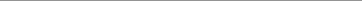 |
| |
展示室で実際に作品を鑑賞しながら、「プライマリー・フィールド」展出品作家と、上智大学国際教養学部教授で美術批評家の林道郎氏に、展示作品について語り合っていただきます。
12月23日(日曜・祝日) 午後1時から5時 |
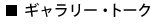 |
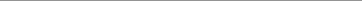 |
| |
12月8日(土曜)、12月15日(土曜)
各日とも午後2時から3時 |
|